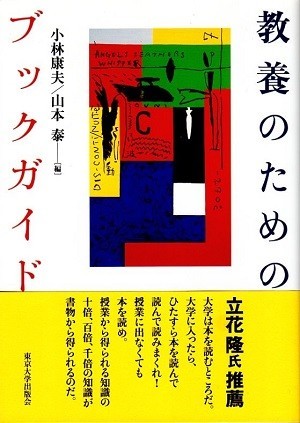推薦書リストの話の続き。
最近、巷の書店で出会って、おおまだ現役だったのかと驚いた本。
桑原武夫 『文学入門』、岩波新書 、1950年1刷(63年31刷改版、2016年87刷)
「文学は人生に必要である」と堂々と述べるその言葉がなんとも眩しい。1950年にはまだテレビ放送も始まっていなかった。外国文学研究者が胸を張って生きていられた時代が、今となってはなんともよい時代だったように見えなくもない。
という個人的感慨はともかくとして、「第一章 なぜ文学は人生に必要か」の著者の論理を少し辿っておこう。小説を読むことによって、読者は著者から「人生そのものへのインタレス ト」(20頁)を受け取る。それによって読者の心には、「行動直前的心的態度」(21頁)が蓄積され、それは現実の我々の行動にも影響を及ぼすことになる。
それと同時に、読書によって「人間について の知識」(22頁)の獲得があることは言うまでもない。「現実に生きて行動する人間について の知識、を供給するものが、ほかならぬ文学なのである。」(23頁)
人生をもっとも充実した仕方で生きるとは、理性も悟性も感性も身体もを含めて全的に行動することである。「人生に強いインタレス トをもち感動しうる心なくしては、よき行動はなく、したがってよき人生のありえないことは、明らかであろう。」(24頁)
人は理性の増強と知識の増加については、つねにこれを力説するが、そしてそれはいかに力説しても十分とはいえないが、しかも、この二者のみをもってしては、人間はついに行動に出ることは不可能なのである。よき行動とよき人生を生み出すためには、さらに人生にインタレス トをもち、感動しうる心と、つねに新しい経験を作り出す構想力とが必要である。ところが人はこの二者の重要性を忘れ、その正しい養成をややともすれば怠りがちである。しかもこの二つのものなくしては、明日のよき生活の建設は決してありえないのである。そしてこれらに糧を与え、これを養成するものが、ほかならぬ文学である。これ以上人生に必要なものが、又とあるだろうか?(24頁)
桑原がここで語っている「文学」は、主に「物語」のことであるように思われるのだが、そうであれば現代の日本人にとって「人生へのインタレス ト」を与えてくれるものとしては、たとえばNHK の大河ドラマ のほうがはるかに身近でありえるだろうし、それはまた、ここで述べられている役割を十分に果たしうるのではないだろうか。というような疑問が、今の私にとって桑原武夫 の断言が羨ましくも思われる所以となる。以上が私の気になることの一点目。
もう一点は、桑原がこのような小説(読書)論を展開したのは、彼が想定しているのが主に19世紀から20世紀初頭のリアリズム小説であるという「前提」があってのことだった、というのが今となってはよく分かるということである。もちろん、桑原がこれを書いたのは1950年であり、彼の述べていることが、その時点における小説の一般的理解として妥当なものだったことは疑うべくもない(後に挙げる彼のリストにはまだカフカ もジョイス も登場していない)。しかし、今の我々が振り返る20世紀の文学史 が、その近代リアリズムの形式をいかに超克するかという問いを巡って書き記されるものであるとすれば、21世紀初頭現在の「読書」論もまた、このように素朴にリアリズム作品だけを対象にすることはできないかもしれない。
さて、そうした留保はともかくとして、「第四章 文学は何を―どう読めばよいか」において、著者は「読書の基準化の必要」を訴えている。
(略)新しいデモクラシーとヒューマニズム の精神による、読書の基準化は今日もっとも緊急を要する仕事であろう。(略)日本でも、各部門ごとにこうした必読書のリストを作成することが、新制大学 の教養課程においてなさるべき、第一の仕事と思われる。もちろんその書目の選定にあたっては、あまりに難解なものをさけること、あまりに多くの冊数をあげてかえって不可能化しないこと、等々、慎重を要するが、さしあたり各大学で、それぞれリストをつくり、それを比較研究して、数年後には全国共通リストのできることを理想としたい。文化国家の教育者は、それくらいの労を惜しんではならないのである。(118頁)
いやはや。なんのことはない、入門者向けの推薦図書リストが欲しいという私の願望は、70年も前に桑原武夫 によってこのように「文化国家の教育者」の使命として掲げられていたのであった。果たしてこの時代に「全国共通リスト」は作られたのだろうか。存在するならぜひ見てみたいものだ。
さて、本書で桑原武夫 は「友人諸君の協力をえて」(120頁)、世界近代小説五十選というリストを作成し、これを掲載している。それをまた例によって、以下に引用させていただくことにする(桑原がこれを共有財産としたがったことを考えれば、このように公表することは著者の意に背くまいという判断です。ご了承願います)。なお原文には文庫名が指定されているが、古い情報なのでその部分は割愛している。
世界近代小説五十選(桑原武夫 『文学入門』、岩波新書 、1950年(1963年改版)、175-177頁)
イタリー
ボッカチオ『デカメロン 』(1350-53)
スペイン
セルバンテス 『ドン・キホーテ 』(1605)
イギリス
デフォオ『ロビンソン漂流記』(1719)
スウィフト『ガリヴァー旅行記 』(1726)
フィールディング『トム・ジョウンズ』(1749)
ジェーン・オースティン 『高慢と偏見 』(1813)スコット『アイヴァンホー』(1820)
エミリ・ブロンテ『嵐が丘 』(1847)
ディケンズ 『デイヴィット・コパーフィールド』(1849)スティー ヴンスン『宝島』(1883)
トマス・ハーディ『テス』(1891)
サマセット・モーム 『人間の絆』(1916)
フランス
ラファイエット夫人 『クレーヴの奥方 』(1678)プレヴォ 『マノン・レスコー 』(1731)
ルソー『告白』(1770)
スタンダール 『赤と黒 』(1830)バルザック 『従妹ベット』(1848)フロベール 『ボヴァリー夫人 』(1857)ユゴー 『レ・ミゼラブル 』(1862)モーパッサン 『女の一生 』(1883)ゾラ『ジェルミナール』(1885)
ロラン『ジャン・クリストフ 』(1904-12)
マルタン ・デュ・ガール『チボー家の人々 』(1922-39)ジイド『贋金つくり』(1926)
マルロオ『人間の条件』(1933)
ドイツ
ゲーテ 『若きウェルテルの悩み』(1774)ノヴァーリス 『青い花 』(1802)ホフマン『黄金宝壺』(1813)
ケラー『緑のハインリヒ』(1854-55、改作1879-80)
ニーチェ 『ツアラトストラかく語りき』(1883-84)リルケ 『マルテの手記』(1910)トオマス・マン『魔の山 』(1924)
スカンディナヴィア
ヤコブセン 『死と愛』(ニイルス・リイネ)(1880)ビョルンソン『アルネ』(1858-59)
ロシア
プーシキン 『大尉の娘』(1836)レールモントフ 『現代の英雄』(1839-40)ゴーゴリ 『死せる魂』(1842-55)ツルゲーネフ 『父と子』(1862)ドストエーフスキイ 『罪と罰 』(1866)トルストイ 『アンナ・カレーニナ 』(1875-77)ゴーリキー 『母』(1907)ショーロホフ『静かなドン』(1906-40)
アメリ カ
ポオ短篇集『黒猫』『モルグ街の殺人事件・盗まれた手紙他』(1838-45)
ホーソン 『緋文字』(1850)メルヴィル 『白鯨』(1851)マーク・トゥエーン『ハックルベリィフィンの冒険』(1883)
ミッチェル『風と共に去りぬ 』(1925-29)
ヘミングウェイ 『武器よさらば 』(1929)ジョン・スタインベック 『怒りのぶどう』(1939)
中国
魯迅 『阿Q正伝・狂人日記 他』(1921)
なるほど、なるほどと、眺めているだけでいろいろ思わされて、たいへん興味深い歴史的資料である。「なぜあれが入っていないのか」式の不満は、この種のリストには不可避なので、あまり言っても仕方ないかと思う。それにしてもスカンディナヴィアの2作には驚かされる。当時はよく読まれていたのだろうか?
さて、ここではひとまずフランスについてだけ見よう。挙げられているのは13作品。『クレーヴの奥方 』と『マノン・レスコー 』はそれぞれ17世紀、18世紀を代表する問答無用の傑作ということで、『告白』は桑原自身による岩波文庫 が近刊だったという事情もないではない(小説に限定するなら『新エロイーズ』のほうが順当な選択かもしれない)。そして19世紀が6作、20世紀が4作となっている。
19世紀の6人(スタンダール 、バルザック 、フロベール 、ユゴー 、モーパッサン 、ゾラ)は、今でも(小説家限定なら)ほぼ同様の名前が挙がるだろう。『従妹ベット』と『ジェルミナール』が現在品切れ(前から言っているがぜひ新訳を出してほしい)。1950年にはすでに評価が動かし難く定まっていた、ということがここから分かる。
問題は20世紀の4作だ。白水社 の『チボー家の人々 』はまだ現役のようだが、それ以外の3作は 品切れして久しい。この4人のなかで、(フランスおよび日本で)今現在かろうじて生き残り、また復活しつつあるのはアンドレ ・ジッド一人だろう。ロマン・ロラン 、ロジェ・マルタン ・デュ・ガール、アンドレ ・マルローの名前は今の時点ではいかにも古色蒼然という感が拭えない。もちろん、私には(近い将来であってさえ)未来の予測はまったくできないのだけれども、「現代の作品」の評価はやはり難しいということを思い知らされる。
そこで、今の私なら20世紀前半の4作品に何を挙げるか、と考えてみた結果は以下のとおり。
22' プルースト 『失われた時を求めて 』(1913-1927)
23' アンドレ・ブルトン 『ナジャ』(1927)
24' アルベール・カミュ 『異邦人』(1942)
25' ボリス・ヴィアン 『日々の泡(うたかたの日々)』(1947)
そう、1950年時点ではまだ『失われた時』の全訳は出ていなかったし、日本で『異邦人』が知られるようになるのももう少し後のことだったのだ。今ならこの2作が外れることはありえないだろう。『ナジャ』が小説かどうか知らないが、シュールレアリスム のない20世紀前半というのも想像し難い。そして昨年が死後60年だったヴィアンのこの作も、その人気は衰えていないはずだ。
と、置き換えてみたら何がどうなるのか自分でもよく分かっていないのだが、これらの作品は今の読者に十分に「人生へのインタレス ト」を掻き立ててくれるだろうか、と改めて思いながら、繰り返しリストを眺めている次第だ(その暇があったら本を読むべきなのだけど)。
クリストフ・マエ Christophe Maé のアルバム『芸術家の人生』La Vie d'artiste より「キャスティング」"Casting"。分かりやすい歌詞。
VIDEO www.youtube.com
Mesdames, Messieurs, emmenez-moi
Je ne veux pas rentrer chez moi
Y'a rien à faire là-bas
Y'a rien à faire là-bas
Medames, Messieurs, me laissez pas
Je ne veux pas rentrer chez moi
Y'a rien à faire là-bas
J'ai rien à faire là-bas
("Casting")
紳士淑女の皆さま、僕を連れていってください
家に帰りたくはありません
あそこですることはありません
あそこですることはありません
紳士淑女の皆さま、僕を見捨てないでください
家に帰りたくはありません
あそこですることはありません
僕にはすることがありません
(「キャスティング」)