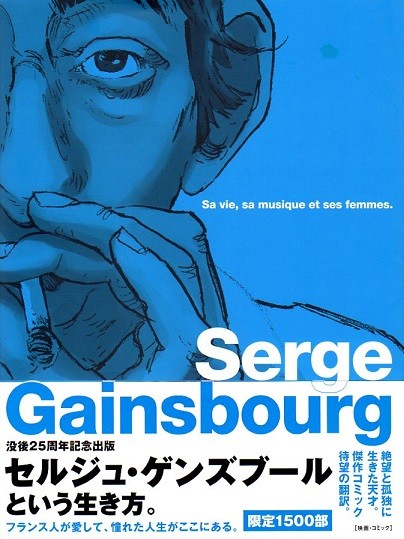「どうしたら良き読者になれるか」、というのは「作家にたいする親切さ」といっても同じだが――なにかそういったことが、これからいろいろな作家のことをいろいろと議論する講義の副題にふさわしいものだと思う。なぜなら、いくつかのヨーロッパの傑作小説を親切に、思いやり深く、けっして急ぐことなく丁寧に、詳細に扱うのが、わたしの計画だからだ。いまから百年前、フロベールは彼の愛人への手紙のなかで、こんなふうのことを語っている。'Comme l'on serait savant si l'on connaissait bien seulement cinq à six livres' ――「わずか五冊か六冊かそこらの本をよく知っているだけで、ひとはどんな学者にもなれるものです。」
本を読むとき、なによりも細部に注意して、それを大事にしなくてはならない。本の陽の当る細部が思いやり深く収集されたあとならば、月の光のような空想的な一般論をやっても、なにも不都合はない。だが、既成の一般論からはじめるようなことがあれば、それは見当ちがいも甚だしく、本の理解がはじまるより先に、とんでもなく遠くのほうにそれていってしまうことになる。
(ウラジミール・ナボコフ「良き読者と良き作家」、『ナボコフの文学講義』、野島秀勝訳、河出文庫、上巻、2013年、53頁)
「親切に、思いやり深く、けっして急ぐことなく丁寧に」本を読むこと。なるほど、ナボコフはとても大事なことを言っている。
それはそうと、当然の如く、フロベールの引用が気になって本を繰る手が(早々に)止まる。とはいえ、検索をかければ瞬時に原典に辿り着けるのだから、いや本当に今の世の中は、20年前には夢だった楽園そのものかとさえ思える。
Tantôt j'ai fait un peu de grec et de latin, mais pas raide. Je vais reprendre, pour mes lectures du soir, les Morales de Plutarque. C'est une mine d'érudition et de pensées intarissable. Comme l'on serait savant, si l'on connaissait bien seulement cinq à six livres !
(Lettre de Flaubert à Louise Colet, jeudi, minuit [17 février 1853], dans Correspondance, Gallimard, coll. "Bibliothèque de la Pléiade", t. II, 1980, p. 247.)
時には僕は少しばかりギリシャ語やラテン語をやりますが、猛烈にではありません。夜の読書には、プルタルコスの『モラリア』をもう一度手に取るつもりです。それは学識と思想との尽きることのない鉱脈です。ほんの五冊か六冊の書物をよく知っていれば、人はどれほど博識になれることでしょう!
(ルイーズ・コレ宛フロベール書簡、1853年2月17日)
http://flaubert.univ-rouen.fr/correspondance/conard/lettres/53b.html
5冊か6冊の本を「よく知る」こと。いや本当にその通りだと思うのだけれど、しかしこの「よく」の一語が難しい。
なにはともあれ、「親切に、思いやり深く」本を読む、というのは本当にいい言葉だと思う。
ケベック出身の女性歌手 Klô Pelgag クロ・ペルガグは、2013年に最初のアルバム L'Alchimie des monstres『怪物たちの錬金術』を発表。批評家から高い評価を得た。たいへん才能豊かな人に違いないが、いやまあしかしなんて変てこりんなんでしょう。とりあえず「カラスたち」を挙げてみる。
La lune est pleine ! La lune est pleine !
La lune est pleine ! La lune est pleine,
Elle est remplie de corbeaux
Et l'archipel ! Et l'archipel !
Et l'archipel, découpé par mes ciseaux("Les Corbeaux")
月は満ちた! 月は満ちた!
月は満ちた! 月は満ちて、
カラスたちで一杯だ
そして列島! そして列島!
そして列島 私のハサミで切り取られて
(「カラスたち」)
これはあるいは「夢」の光景でもあるのだろうか。